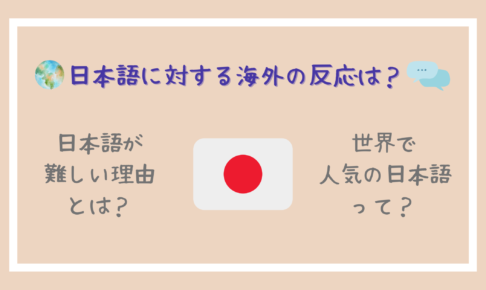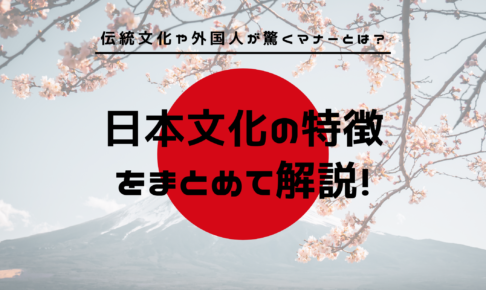こちらは、このような方を対象とした記事です!
- 日本語は他の言語と比べて難しいの?と疑問に思っている方
- 外国人は日本語のどこを難しいと感じているのか知りたい!という方
- 周りの外国人に日本語を教えたい方
- 日本語教師になることに興味のある方
この記事では、以下の内容を詳しく解説しています!
- 日本語は他言語とくらべて難しい言語なのか?
- 日本語のどこが難しいのか?
- 外国人に教える際のコツ
この記事を読めば「日本語の何が難しいのか?」「どうやって日本語を教えたらいいのか?」を知ることができます◎
目次
日本語は難しい言語なの?
そもそも日本語は日本語ノンネイティブの外国人にとって習得が難しい言語なのでしょうか?
結論としては、「とても難しい」と思います。
理由としては、①アメリカ国務省の発表する「外国語習得難易度ランキング」と②現役日本語教師である私自身の見解の2つを挙げたいと思います。
日本語は習得が難しいと言える理由① アメリカ国務省のデータ
1つ目の理由は、日本で言うと外務省にあたるアメリカ国務省が公表しているデータによります。
他国との交渉のためにアメリカ人外国官が「ビジネスレベル」の語学力を習得するための難易度を各言語ごとに全4レベル(カテゴリー)に分けています。
| 難易度 | 言語種別 |
| カテゴリー1(最も易しい) | イタリア語、スペイン語、フランス語など |
| カテゴリー2 | ドイツ語、インドネシア語、スワヒリ語など |
| カテゴリー3 | ヒンディー語、ロシア語、モンゴル語など |
| カテゴリー4(最も難しい) | 日本語、アラビア語、韓国語、中国語など |
参照: アメリカ国務省HP(英語)
このデータによると日本語はアラビア語や韓国語と並んで最も難しいカテゴリー4に分類されています。
日本語は習得が難しいと言える理由② 現役日本語教師の実体験
日本語を教えることが仕事である日本語教師の私自身も常に「日本語って難しい!」と感じています。
これはもちろん教師だけでなく学生にとっても同じことで、よく「日本語は難しすぎる!」と言われます。
では、外国人学習者は日本語の何が具体的に難しいのか、どんなところでつまずくのか、現役日本語教師の目線から解説していきます。
また日本語を教える際のポイントも載せていますので良ければ参考にしてみてください◎
【日本語のどこが難しい?①】表記文字の種類が多い
日本語にはひらがな、カタカナ、漢字の3つがあります。
初級学習者は似たような表記の多い、ひらがなとカタカナの違いがなかなか覚えられない人が多いです。
「ひらがなだけでも覚えるのがやっとなのに、カタカナも漢字もある・・・」となると、使用する文字の種類が多いということで、”日本語は難しい” ”日本語を学習するのは大変だ”と感じてしまう人も多いようです。
さらに3つの文字のうち、非漢字圏の学習者にとっては「漢字」が最大の壁となります。
漢字に馴染みのない学習者にとっては、「膨大な数の漢字の書き方・構造を覚えなければいけない」という点が非常に難しい、と感じているようです。
では、教える際にはどのような部分に気を付けて教えるのが良いのでしょうか。
対策:読めればいい漢字と書けなければならない漢字の区別をしてあげる
ここではよく使う漢字と、あまり使わない読むことができればいい漢字を示してあげると良いと思います。
現在、日本で採用されている「常用漢字」は、2010年11月の内閣告示で「2136字」と定められています。
ですが、学習者にとっても全て覚えるというのは負担が大きいので、使用頻度や必要度などを言ってあげるのも一つの方法だと思います。
【日本語のどこが難しい?②】音読みと訓読みがある
漢字は、書き方・構造が難しいだけではなく「訓読み・音読みがあり、一つの漢字に読み方が何通りもある」という点も日本語の難しいところです。
例えば、「上」という漢字は一つだけで、「上(うえ)」「上(あ)がる」「上昇(じょうしょう)」「上(のぼ)る」とさまざまな読み方が存在しています。
学習者にとって「読み方をすべて覚え、どんな時にどのような読み方をするのか覚える」ことは、かなり難しいでしょう。
対策:規則パターンを教え、多くの文章に触れてもらう
音読みと訓読みの絶対的な判別方法というものは、残念ながらないようです。
ですが、「漢字が複数続く場合は音読み」「送り仮名が付く場合は訓読み」といったいくつかのルールがあります。これらのルールには、例外があるため絶対とは言えないものの、一つの傾向パターンとして教えてみましょう。
あとはできる限り多くの文章に触れることで、自然と読み方に慣れていってもらうようにしましょう。
日本語の本や教科書にある文章を通して、「読み方が分からない場合はその都度調べて確認してみる」というように、地道な努力を積み重ねていくことが大切です。
【日本語のどこが難しい?③】日本語の発音構造
次に、日本語の発音です。発音は特に学習者の母語の影響を受けてしまうことが多く(母語干渉と呼ばれています)自分の母語にない発音がなかなかうまくできない場合があります。
例えば、日本語では「たんす(tansu)」と「ダンス(dansu)」は[t]と[d]の違いによって意味が異なります。
[t]は無声音、[d]は有声音なのですが、中国語や韓国語ではこの違いで意味を区別しないため、聞き分けたり発音したりすることが難しいです。そのため、中国語や韓国語の母語話者は日本語の「タ」と「ダ」の区別がうまくできず、「私」が「わたし→わだし」となってしまう人も多いです。
他にも、特殊拍と呼ばれる長音(伸ばす音:おばさんとおばあさん)や促音(小さい「っ」の音:切手と来て)撥音(「ん」の音:みなさんがみんなさんになる)などに対して苦手意識を持っている学習者が多いです。
対策:学習者の発音ミスの原因を考える
学習者の発音のミスには様々な原因が考えられます。また先ほど述べた母語の影響も、一口に母語の影響といっても実は様々な原因が考えられます。
学習者の母語干渉には1「発音ができない」2「聞き分けられない」3「どちらがどちらかわからない」という3つの原因が考えられると述べられています。
1は、知識があるのに発音の仕方がわからずうまく発音できない場合。
2は、発音はできるが、教師の発音を聞き取れず、間違った発音で理解してしまった場合。
3は、発音も聞き取りもできるが知識がないため使い分けられない場合。
そのため、教師は学習者がなぜその発音になってしまうのか、原因について分析する必要があります。
単に「違います」だけではなく、なぜ学習者が間違ってしまったのかに注意して発音指導ができると、学習者自身も自分の癖や間違いやすい部分に気がつき、気をつけることができるので、発音が改善されやすいです!
参考文献:林良子『日本語の発音―教室での気づきから 論文投稿まで―』
対策:日本人の発音に慣れさせる
日本人の発音に慣れるためには、実際に日本人が話しているのを真似することが一番ですよね。
授業の中ではシャドーイングや、ラジオやドラマなどの生教材を使ってみるというのも一つの方法だと思います。
自然な日本語というのはどういうものか、学生がイメージしやすいようにしてあげましょう。
【日本語のどこが難しい?④】似ている語彙・表現が多い
日本語が難しいといわれる原因は、その表現の多さにもあります。
日本語には同じような状況を表す表現が多くありますが、うまく使い分けなければ相手に失礼になってしまうこともあります。
例えば、お昼に食べるごはんのことを表す言葉だけでも、「お昼ごはん」「お昼」「昼」「ランチ」「昼めし」「昼食」と6つも言い方があります。
この表現の中には上司にも使えるものや、仲の良い関係でしか使えないものなどがありますよね。
この他にも、「わざわざ」と「せっかく」、「つい」と「うっかり」のように、似たような表現も多く出てきます。
対策:使用場面を整理する
ここで大事なのが、使用場面です。先ほどの、お昼ごはんの例だと、「昼」「昼めし」はカジュアルでどちらかというと男性が使うことが多い表現ですよね。
他の表現は男女関係なく使いますが、「昼食」や「お昼ごはん」は丁寧なイメージがあります。
この中で言うと、一番「お昼ごはん」を使っている人が多いですから、他の表現は知っていればいいものになりますね。
このように誰に対して使うのか、使用頻度などについて説明してあげると学生も整理がしやすくなります。
もう一つの例の「わざわざ」と「せっかく」も「手間や時間をかけて」と言う部分の意味はほとんど同じですが、使用場面が異なる時があります。
ある会社員の出張先での出来事で考えたとき、「わざわざ」は「別にする必要がないことを意図的に行う」 場面で使い、後には、困難や労力を費やすので、本来は行う必要がないことがきます。
例)会社員:わざわざ来たのに、案内もしてくれないなんて…ひどい会社だ。
「せっかく」は「あることを行うときに、ついでに他のことも一緒に行うこと」 で 後には、比較的望ましく、行えたら良いことがきます。
例)出張先の会社:「せっかく来ていただいたので、観光案内もしますよ!」
会社員:「ありがとうございます!」(いい会社だ!)
このように場面で説明するとわかりやすいですよね!
【日本語のどこが難しい?⑤】オノマトペが多い
日本語は、オノマトペの数が非常に多い言語です。
比較的オノマトペが多いとされている中国語と比べても、日本語のオノマトペの数は圧倒的に多いです。
特に欧米ではほぼ使われていないため、日本語を学ぶ際に「オノマトペが難しい」と感じる学習者がとても多いのです。
オノマトペの例
- ドンドン
- ザーザー
- バラバラ
- つるつる
- きらきら
- ぐちゃぐちゃ
- ぐずぐず
では、具体的にオノマトペの何が難しいと感じているのかというと・・・
「日常生活でよく使われるから覚えたいけど、数が多すぎて大変」「それぞれのオノマトペがどんな音や様子を表すのか、全く想像ができない」「それぞれのオノマトペに相当する母語がなく、翻訳ができない」というところに壁を感じています。
対策:オノマトペが表している実際の音を聞かせる・画像を見せる
物が発する音を表す「擬音語」は実際の音を聞いてもらう、音のない様子や状態を表す「擬態語」は画像を見せて説明する方法がよいでしょう。
たとえば雨の音を表す「ザーザー」という擬音語を教える場合、Youtubeで「ザーザー 雨」と検索してみます。すると少し激しい雨が降っている動画が出てくるので、その動画を見せながら教えると学習者にとってとても分かりやすいです。「ザーザーではなく、ガーガーじゃない?」と人によって感じ方が異なるので、どう聞こえるかを学習者同士で話し合ってみるのも面白いかもしれません◎
一方で、擬態語を教える場合は漫画を活用する方法もおすすめです。「ドキドキ」や「ドンドン」という擬態語は、漫画の多くのシーンで使われています。一つの擬態語についていくつかのシーンを見せることで、場面や画像の様子から意味を読み取ることができるようになります。
【日本語のどこが難しい?⑥】主語の省略が多い
日本語は、主語を省略したり曖昧にしたりすることが多いです。
英語をはじめとしたヨーロッパの言語は、基本的に主語を省略しません。そのため主語の省略に慣れておらず、文の流れから主語を考えるのに苦労する学習者が多くいます。
例)日本語の主語の省略
私 :明日、どこで会う?(Where are we going to meet tomorrow? )
友達:買い物したいから、渋谷はどう?( I want to do shopping, so how about Shibuya? )
私 :いいね!(Sounds good! )
対策:文章や会話の中で主語を見つけてもらう
主語の省略に慣れるためにはさまざまな文章や会話の中で、主語は誰なのかを見つける練習をすることが大切です。
例えば、上記「日本語の主語の省略」の例で示したような会話を提示して、文脈を読み取った上で主語が誰なのかを学習者に見つけてもらいます。
文章や会話の難易度は、学習者のレベルによって変えていくのがよいでしょう◎
この記事を読んで日本語教師に興味が出た!日本語を教えてみたい!と思った方は、日本語教師になるためのスクールの資料請求をしてみてください!
日本語教師アカデミーでは無料でお近くの日本語教師養成講座の資料を一括で取り寄せることが可能です◎
まとめ
- 日本語は難しい言語である。
- 日本語の難しさ①表記文字の種類が多い
- 日本語の難しさ②日本語の発音構造
- 日本語の難しさ③音読み・訓読みがある
- 日本語の難しさ④似ている語彙・表現が多い
- 日本語の難しさ⑤オノマトペが多い
- 日本語の難しさ⑥主語の省略が多い
すーみん
運営情報最新記事 by すーみん (全て見る)
- 美しい日本語・綺麗な日本語を話すためのポイント4選!勉強の仕方やメリットについても紹介!◎ - 2021/7/3
- 【文法用語】い形容詞・な形容詞って?見分け方や活用の仕方など徹底解説! - 2021/6/1
- 【他校の半額?!】(財)国際生涯学習研究財団の日本語教師養成講座! - 2021/5/4

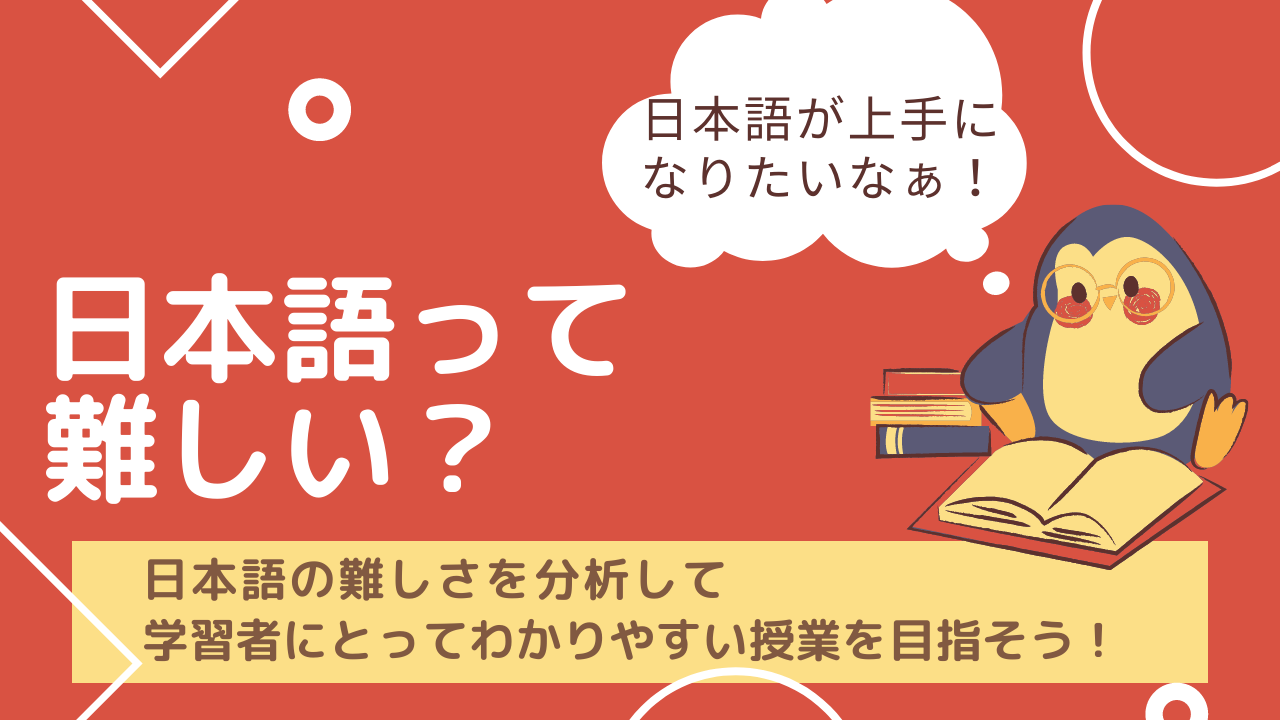

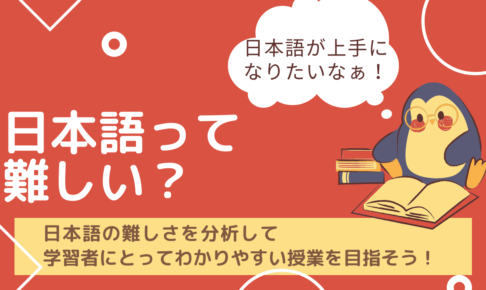


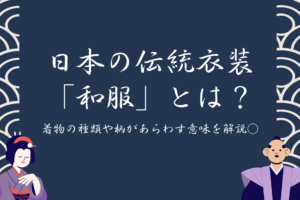
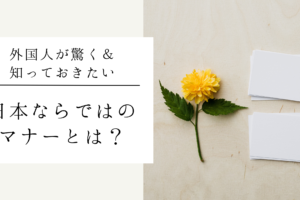
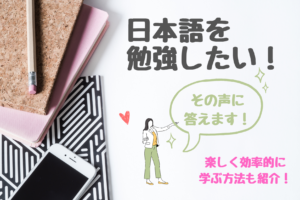


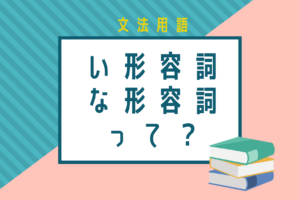
-39-300x200.png)
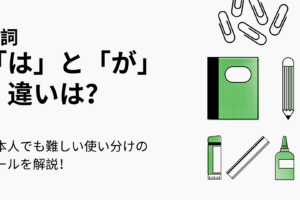


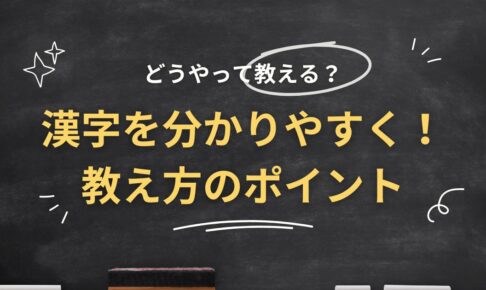
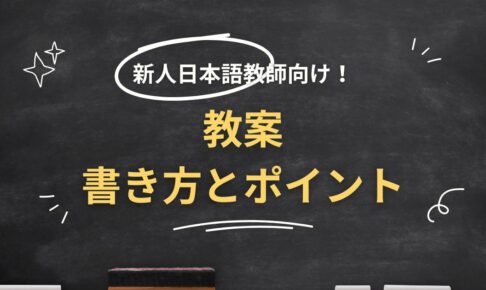
-39-486x290.png)